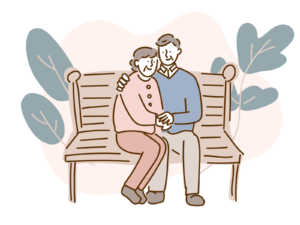「ここら辺に住んでると、車がないと本当に不便よ」
「免許はまだ期限が残っているけど、車はない。でも、免許証は持っていたい」
その言葉が、心に残っています。
この日、僕はあるご利用者様の病院受診に付き添わせていただきました。
本来は担当のケアマネジャーが同行予定でしたが、急遽予定が合わず、代わりにサポートさせていただきました。
■ 片道30分、診察と買い物を含む半日サポート
ご自宅から病院までは車で片道30分。
病院に向かう前に、まず病院内のATMに立ち寄りました。
ご自宅周辺にはATMがなく、こうした“ついでの用事”ができるのも、福祉タクシーならではの対応だと思っています。
診察中は、医師の説明や処方薬の内容を一緒に聞き、メモを取りながらご本人の理解をサポートしました。
また、その場でケアマネジャーや訪問看護ステーションの看護師に向けて情報提供も行いました。
単なる付き添いにとどまらず、「連携」の担い手としても機能することができるのが、強みだと思っています。
■ 生活の“あたりまえ”が、困難になる現実
病院からの帰り道、ご本人がふと漏らしたのが冒頭の一言。
「車がないと、本当に不便なのよね」
バスの本数は限られ、タクシーはすぐに呼べるわけでもない。
“ちょっと買い物に”“通帳記帳に”“診察に行くだけ”が、実は大きな壁になっている方が地方には数多くいらっしゃいます。
最近では「高齢者の免許返納」が全国的に進められています。
安全の面ではとても大切な取り組みだと思います。
しかし、都市部と異なり、公共交通の選択肢が乏しい地域では、免許返納=生活の困窮に直結することも。
家族に勧められて免許証を自主返納したが、それが「外出を諦める」という結果になっている人もいるのではないか・・・それでご本人の生活の質はどうなるのか・・・
その現実を肌で感じるたびに、「移動の自由」はただの利便性ではなく、**“暮らしの根っこ”**なのだと実感します。
■ 日常の中にこそ支援がある
病院受診が終わった後、ご本人のリクエストでスーパーに寄りました。
最初は生協コープでお買い物。
そのあとに立ち寄ったプラッセ食品館では、なんとカルピスの500mlペットボトルを20本購入されました。
「家内が好きでね」と笑顔で話されました。
買い物袋には入りきらないため、店員さんに相談して段ボールをもらい、車まで運ぶのをお手伝い。
ちょっとした荷物の持ち運びや、荷物の整理など、一般のタクシーでは対応しづらい細かな部分に手が届くのも、福祉タクシーの良さだと感じます。
■ 支援の幅は「目的地の数」だけ広がる
福祉タクシーというと「通院のための乗り物」と思われがちですが、実際にはそれだけではありません。
・診察中、看護師や医師へ、本人の症状などを代弁・医師の説明を本人へ分かりやすく説明
・薬の内容確認
・ケアマネや医療職への情報提供
・買い物やATM、銀行など生活に直結する用事の代行や同行
こういった支援が、“その人の生活そのもの”を支えています。
今回のように、
「診察」→「薬局」→「ATM」→「コープ」→「プラッセ」→「自宅送迎」
といった複数の目的地を1本のルートでまわることも、柔軟に対応しています。
■ もっと自由に、もっとその人らしく
“介護”や“福祉”というと、どうしても「制限された支援」のイメージが強くなりがちです。
でも本来は、その方の「したいこと」「必要なこと」に合わせて支援を組み立てていくのが理想のかたち。
「カルピス20本」も、「ATMだけで終わらないお出かけ」も、
その人にとっては、かけがえのない“大事な暮らしの一部”です。
福祉タクシーむすびでは、その“自由な暮らし”を守るために、
できる限り柔軟に、できる限り寄り添った支援を提供したいと思っています。
■ 最後に――地域の「足」としての責任
繰り返しにはなりますが、福祉タクシーは、単なる移動の手段ではありません。
地域で暮らす人たちの「安心」や「自立」「尊厳」を守るためのインフラでもあります。
便利な都市では見えづらい課題。
しかし地方には、車が1台減ることで、暮らしが立ちゆかなくなる世帯が確かに存在します。
だからこそ、その“あたりまえの暮らし”を支える足でありたい。
誰かの一歩を、支える力になれたらと思っています。
🌿【福祉タクシーむすびでは】
・通院やお出かけの送迎+付き添い
・買い物や銀行・役所などの同行サポート
・ケアマネや医療職との情報連携
・荷物運搬、生活サポートも柔軟対応
📍薩摩川内市・近隣エリア対応
📞お気軽にお問い合わせ・LINEからも予約受付中です。