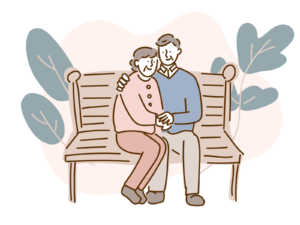退院の日、笑顔と連携が支えた「ただいま」
退院のサポートは、単に病院から自宅へお送りするだけではありません。
それは、「また、ここで暮らす」という再出発の日。
今回、僕がサポートさせていただいたのは、冬にご入院されていた70代の男性の退院と帰宅の支援でした。
空は快晴。まるで、退院を祝福するかのような青空が広がっていたこの日――
久しぶりの帰宅を支える一連の流れの中で、たくさんの気づきと学びがありました。
1. ご自宅に帰るということ
入院されていたのは、肺のご病気が理由だったとのこと。
ご本人は長期の療養を経て、ようやくご自宅に戻られることに。
ご家族からは「お風呂のことが心配で…」という声も聞かれ、退院は喜びと不安が入り混じるものであることを感じました。
病院の玄関前にて、ご家族――奥様と娘さまと合流。
奥様は明るく冗談を交えながらご本人に話しかけ、その様子を見てご本人がふっと微笑んだのがとても印象的でした。
その表情には、「ああ、家に帰れるんだな」という安堵がにじんでいました。
2. サポートの始まり:ケアマネとの連携と待機
今回のサポートは、事前に担当ケアマネジャーさんからの連絡がきっかけでした。
「ご家族の車で帰る予定だけど、移乗が難しいかもしれない。念のためスタンバイしていてもらえますか?」
こうした“かもしれない”に備えて動けるのも、福祉タクシーの柔軟性ならでは。
実際、ご家族のお車への移乗が難しいことが現場で判明し、急遽その場でサービスをご利用いただくことに。
ご本人にもご家族にも、しっかりサービス内容をご説明し、安心してご乗車いただきました。
3. 車椅子でのご乗車:慎重な対応の積み重ね
ご乗車いただいたのは、タントスローパー。
しかしご本人は180cm近くあり、車高はスレスレ。
後部ドアの上部と頭が接触しないよう、慎重に声をかけながらの対応となりました。
力を入れて車椅子を押し上げる場面もあり、安定を保つのに注意を要しました。
急いで動かすと不安を与えてしまうため、焦らず、ひとつひとつの動作を丁寧に。
この経験から、「電動ウィンチはやはり必要だ」と強く実感した次第です。
4. 自宅に着いてから:安心の仕組みとご家族の支え
ご自宅には、すでに昇降機が設置されていました。
リビングへと通じる扉から直結していて、段差や階段の心配もなく、すぐにご本人の生活空間へと移動できる構造でした。
操作は娘さまが担当されており、とてもスムーズ。
本人も不安な様子は一切なく、まるで以前から使い慣れていたかのように自然にリビングへと戻られました。
「家に帰る」とは、物理的な移動だけでなく、“自分の場所”に帰ってくるという心理的なプロセスでもある――
そのことを、静かに柔らかくなっていくご本人の表情が教えてくれました。
5. 支援のつながりが生む穏やかな日常
午後には、担当者会議が開催されました。
そこにはケアマネジャーさんをはじめ、介護保険サービスに関わる多職種の方々が集まり、今後の支援計画が話し合われました。
「支援とは、一人ではなく、チームで行うものだ」ということ。
退院支援は、その人のこれからの生活を支える“土台作り”であり、家族・専門職・地域資源がうまく連携してこそ成立するものなのです。
僕自身も、ケアマネさんからあらかじめ情報を得ておくことで、家族への説明がスムーズに行われ、現場での信頼形成がスピーディーになることを実感しました。
6. この支援を通して学んだこと
今回の支援では、以下のような学びや気づきがありました。
- ケアマネジャーとの情報連携の重要性
- 「もしも」に備える柔軟な体制づくり
- 怪我をさせないための一つひとつの動作の丁寧さ
- 電動ウィンチや車両選定の改善点
- 家族の関わりが本人の安心感に与える影響
そして何より、「誰かの生活の再スタートに立ち会えることの尊さ」。
この仕事の魅力はまさにここにあるのだと、改めて胸に刻まれました。
まとめ
退院支援とは、単なる“病院から自宅への移動”ではありません。
それは、「自分の暮らしを取り戻す」ための第一歩を支えること。
ご本人、ご家族、ケアマネ、支援者たちが一体となって、
“その人らしい日常”が再び動き始める瞬間を支えているのです。
笑顔、気配り、連携、そして静かな「ただいま」の言葉の代わりになるような微笑み。
その一瞬一瞬に、大きな価値がある。
そんな仕事に携われる喜びを、心から感じた一日でした。